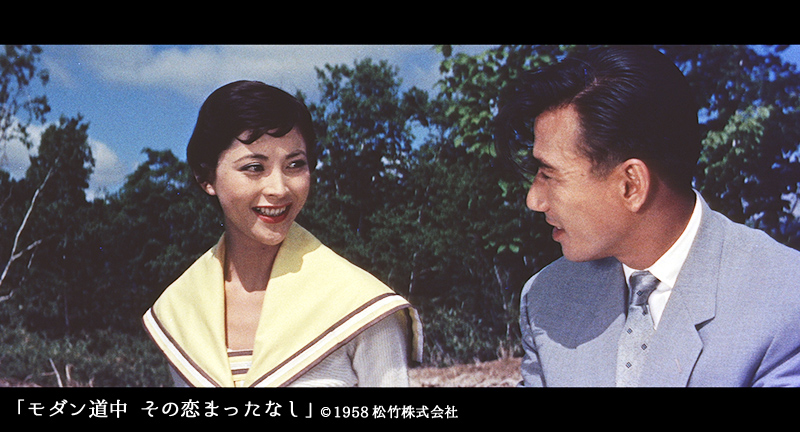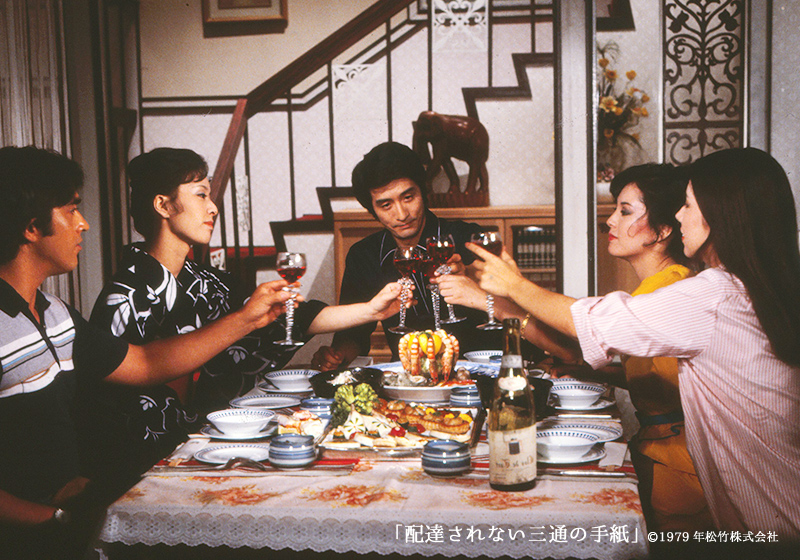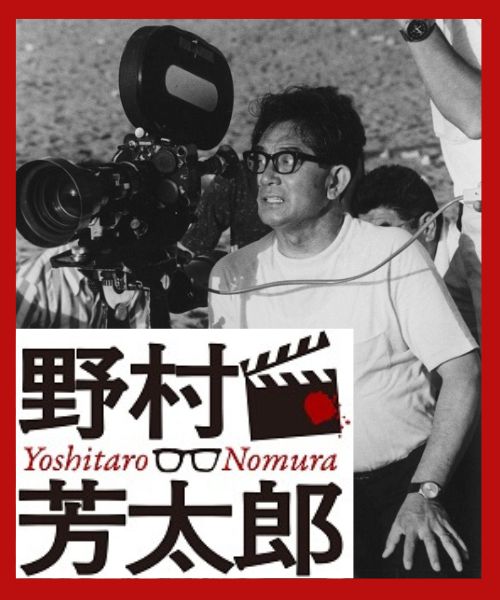連載コラム「銀幕を舞うコトバたち(44)」よその人だよ、知らないよ。 父ちゃんじゃない。
カテゴリ:コラム "銀幕を舞うコトバたち"
日本で映像化された小説が最も多い作家と言えば、おそらく松本清張である。映画はすでに30本以上が製作されているし、テレビドラマも単発物、連続物を含め数百本に及ぶだろう。理由は松本清張の小説そのものが面白いからに他ならないのだが、もう一つは作品テーマの普遍性にある。事件の背後には必ず貧困や差別や格差といった人間の欲望に根差した社会問題が横たわっていて、これが時代を経ても色褪せない。

子どもへのDVを描いた『鬼畜』もまさにそんな映画である。どこにも逃げ場のない社会的弱者である子どもたちが愚かな大人に虐待される光景を見て、なんだ、日本はちっとも変わっていないじゃないかとは誰もが思うことだろう。『鬼畜』に描かれるような事件の報道に、ぼくたちは映画の公開から40年以上経った今も日々接している。 たとえば、劇中での主婦のこんな言葉は今でもどこかで聞きそうだ。
「若い人がやることは恐ろしくて…。地獄だね、まったく」
ラスト近くで、役所の福祉担当者もこう漏らす。
「若い親に子どもを育てる能力がないというのか、意志のないのが増えてね…」
物語の主人公は零細印刷業者の社長。冴えない男なのだが、緒形拳がそのダメっぷりを演じて抜群にうまい。彼は岩下志麻演じる妻がいながら、小川真由美演じる愛人も囲っている。しかも妻には子どもができなかったが、愛人との間には3人の子がいる。ところが、火事で会社の経営が行き詰まり、養育費が滞ると、小川真由美は意を決して緒形夫婦の元に乗り込んでくる。そして、子どもたちを置き去りにしたまま姿を消してしまう。

登場人物は少なく、生々しい生活描写の中で憎しみや怒りといった感情表現がドラマを駆動させていくため、求められるのは役者の力量である。序盤で目を奪うのは岩下志麻と小川真由美の演技だろう。ともに不自然さや過剰さを感じさせない、すれすれのところで踏みとどまり、女の傲慢や動揺を毒々しい色で隈取って対峙する。深夜、障子一つを隔てて互いの気配をうかがうあたりは背筋が寒くなるほどだ。迫力も凄味も色気もある。2人を大蛇にたとえれば、板挟みとなった緒形は無力なカエルにしか見えない。
このあたり、野村芳太郎の対象を突き放した冷徹な演出が冴えわたっている。
それまで夫と愛人との関係をつゆほども知らず、突然、子どもを押し付けられた岩下の激しい憎悪が観る者をたじろがせる。一番下の幼児を故意か偶然かわからないように衰弱死させてしまうと、残る3歳の長女と6歳の長男も、早く始末するようにと夫に圧力をかける。追いつめられる緒形の顔も徐々に鬼畜の形相を帯びていく。
緒形と岩下の濃厚な演技があるから、子どもたちの純真が際立ち、痛々しい。『影の車』、『砂の器』、『震える舌』と、野村映画では子役が重要な役割を果たすことが多いが、本作もまた彼らの芝居に負うところは大きい。とくに一度見たら忘れられないのが長男(岩瀬浩規)の目。澄んだ真っすぐな眼差しが大人たちの無責任なエゴイズムを射抜く。

警察署で、自分を殺そうとした父親と対面した少年のたどたどしい言葉もこの目があるから心を揺さぶる。
「ちがうよ、父ちゃんじゃないよ」 「父ちゃんなんかじゃないよ、知らない人。 父ちゃんじゃない」 「よその人だよ、知らないよ。父ちゃんじゃないよ」
何度も口を衝いて出る否定の言葉は父を「犯人ではない」と一生懸命庇っているようにも聞こえるし、父を敢然と拒絶しているようにも受け取れる。 少年の視点に立てば、『鬼畜』は明らかに「父殺し」の映画だ。息子が父の生き方や考え方を否定し、父という壁を乗り越え、つまり精神的な「父殺し」を行って成長していく姿は小説でも映画でも繰り返し描かれてきた。しかし、6歳で、しかもこんな不幸なかたちで「父殺し」に直面しなければならなかったところに、この映画の絶望も哀切もある。そして、多くの「父殺し」の物語に用意されている和解が、ここにはない。少年が父を許す日は訪れるのだろうか。
文 米谷紳之介