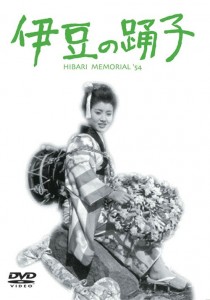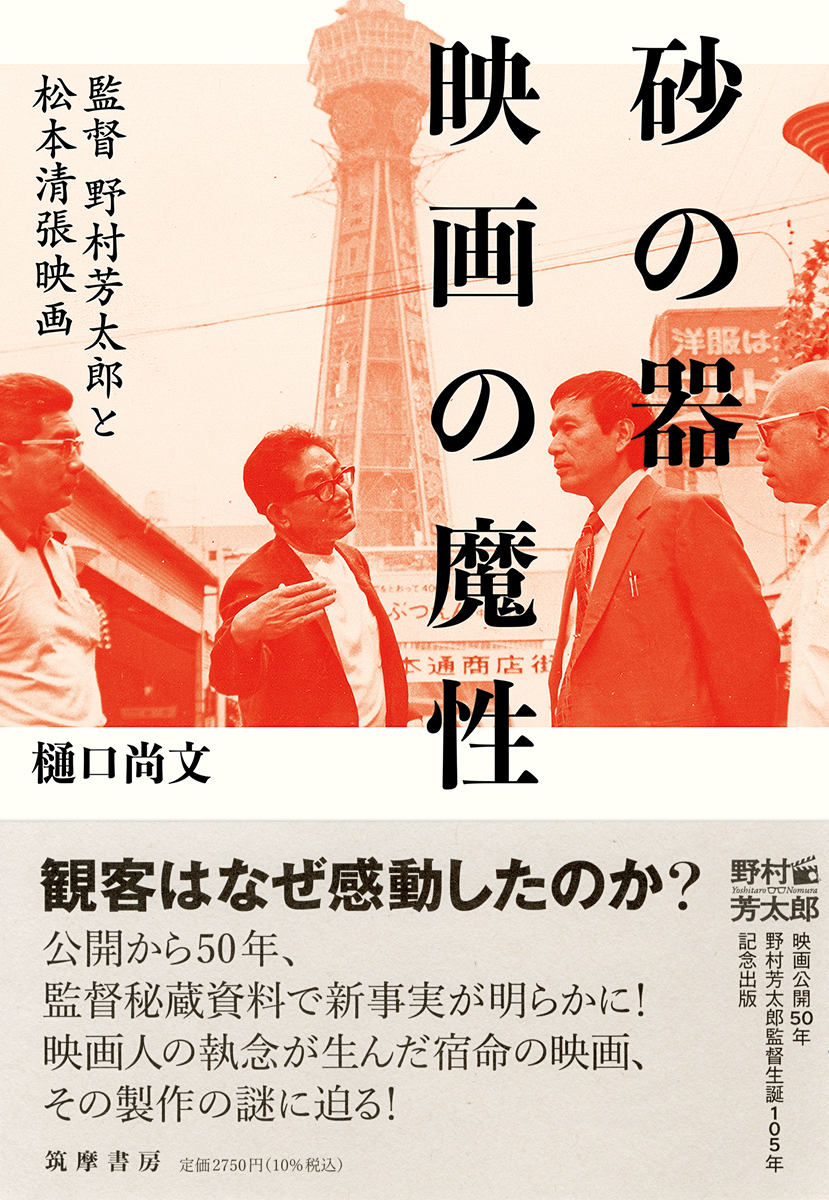連載コラム「銀幕を舞うコトバたち(32)」あっ、活動連れてってくださいね。
カテゴリ:コラム "銀幕を舞うコトバたち"
“歌謡界の女王”美空ひばりが“銀幕の女王”でもあった事実を知らない若い映画ファンは案外多い。それだけ歌で残した足跡が大きく、未だに歌う姿の印象が強烈なわけでもあるのだが、美空ひばりは生涯に170本近い映画に出ている。それも1949年に映画デビューし、映画から離れたのが1971年と、女優としての活動期間はわずか20年ほど。しかもほとんどが主演作である。
同じ1937年生まれのスターに加山雄三がいるが、美空ひばりのほうが出演本数は断然多く、まぎれもなく日本映画の黄金期を支えた一人だったことを証明している。出演作の多くは時代劇で、中村錦之助(のちに萬屋錦之介)、大川橋蔵、鶴田浩二、高倉健といった錚々たるスターと共演した。

そんな美空ひばりが『伊豆の踊子』のヒロイン「薫」を演じたのは17歳のとき。言わずと知れた川端康成の小説が原作で、戦前には田中絹代主演で最初の映画化がされている。2度目が本作。その後も鰐淵晴子、吉永小百合、内藤洋子、山口百恵で映画化されているから、ある時期まではスター女優の登竜門と言っていい作品だった。この中で美空ひばりが原作の踊り子のイメージに一番近いように思うのはぼくだけではない。彼女を最もよく知るルポライターの竹中労は『完本 美空ひばり』で、他の女優は美しすぎて哀れに欠けると評し、こう続ける。
「美空ひばりは、無造作に彼の文学を跨いでこえた、みごとに旅芸人であった」
彼とはもちろん川端康成である。
9歳で舞台に立った美空ひばりは売れる前は前座歌手として地方巡業をした経験もあり、14歳のヒロインを演じるのにぴったりの小柄でもあった。しかし小さな体から放つ磁力は半端でない。彼女が最初にスクリーンに現れるのは修善寺の桂川にかかる橋。人を待つ様子でそわそわしている。その初々しい姿を旅館の2階から凝視するのが、彼女に惹かれる一高の学生。演じる石浜朗の目力がすごい。容貌はダルビッシュ有にそっくりで、切れ長の涼しい目は終始、踊り子を射抜くように真っすぐ向けられる。

対する美空ひばりは口元の表情と低い声だ。ためらいがちなようで、強い意思を秘めているのがわかる。出会いから別れまでうつむき加減のシーンが多いにもかかわらず、感情表現が豊かで、とても17歳とは思えない。すでに芝居の「間」も「リズム」も心得ている。心の清らかさ、自分の境遇を思うときの愁い、そこはかとない色気。これらが巧みにブレンドされたヒロインの人物像が彼女の演技によってくっきり浮かび上がってくる。
物語の背景に横たわるのは、昭和初期の日本には厳然とあった差別や格差の意識である。踊り子の一行は温泉町や農村の人々に蔑まれ、「物乞い旅藝人 村へ入るべからず」と書かれた道の立て札にも出くわす。踊り子たちと一緒に旅する学生の心にもそのような感情が全くないと言ったら嘘だろう。

こうした時代の空気を監督デビュー3年目の野村芳太郎は甘い感傷に流されない冷徹な目で見つめる。無駄なカットやセリフを嫌い、薫と学生の言動のスケッチとその周囲で起こる小さな出来事の描写を通して物語を静かに進めていくのだ。原作にある有名なセリフ「ほんとうにいい人ね。いい人はいいね」もここにはない。山あいの農村の老人や子どもの顔をドキュメンタリー映像のようにとらえ、ラストの港での別れのシーンもまるで当時のニュース映像のように見せてしまう。
だから、一緒に旅することになった学生と薫が仲間たちと少し離れて道を行く無邪気なシーンは、雲間に射した光がつくる陽だまりのような温もりを感じさせる。
「あっ、活動連れてってくださいね」
弾むような声で薫が学生に語りかける笑顔が愛らしい。この時代、映画は庶民の最大の娯楽だったのである。その約束が果たされることはないのだが、もし実現していたら、何を観たのだろうか。
公開から60年以上経った今も、本作には滅びゆく旅芸人への惜別や遠慮がちに生きる人々への共感のようなものが息づいていて、心にしみる。松竹大船調の伝統と当時35歳の新鋭監督・野村芳太郎らしい進取の精神が合わさった出色の文芸映画である。
文 米谷紳之介
2025年から始動しました映画監督 野村芳太郎 再発見 & 再評価プロジェクト始動を記念しまして2019年野村芳太郎監督生誕100年に米谷紳之介さんにご執筆いただきましたコラムを再度、ご紹介してまいります。