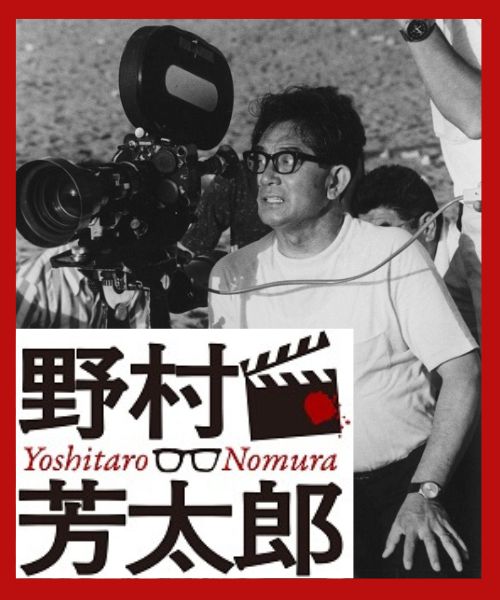連載コラム「銀幕を舞うコトバたち(48)」
勘というやつを働かせないといけないよ、勘というやつを。
カテゴリ:コラム "銀幕を舞うコトバたち", 松竹映画100周年
日本初の映画専門劇場「電気館」が浅草にオープンした1903年は、小津安二郎と清水宏の2人が生を授かった、大変めでたい年でもある。
ともに日本映画の巨匠となるわけだが、デビューは清水宏のほうが早かった。1922年に松竹蒲田撮影所に入社すると、2年後の21歳のとき、監督に昇進。小津は清水に1年遅れで入社し、24歳で初メガホンを取った。
互いを認め合い、生涯に渡って親しい仲は続いたが、作風はまるで異なる。セット撮影が中心、カメラをローアングルに固定した小津に対し、清水宏はロケを好み、移動撮影でその真価を発揮した。

2人について笠智衆が『大船日記 小津安二郎先生の思い出』にこう書いている。
「小津先生はスマートで洒落者。清水オヤジはデップリしてキンカン頭で、夏場は『涼しいから』と、ランニングと半ズボンでいるような人です。お二人が並んでいると、大学教授と鉄工場のオヤジが一緒にいるようでした。まったくおかしなコンビです」
清水宏は根っからの子ども好きとしても知られる。終戦後、戦災孤児を10人ほど引き取ると、私財を投げ打って買った伊豆の山の家で育てた。その子どもたちを起用してオールロケーションで撮ったのが長編映画『蜂の巣の子供達』である。
子ども好きで、ロケ好き。さらに清水宏がもう一つ好んだものに、ひなびた温泉を挙げられる。そして、この3つの要素が揃った傑作が『按摩と女』だ。

出だしは按摩の徳市(徳大寺伸)と福市(日守新一)の2人が、伊豆の山道を勝手知ったる様子で歩くシーン。2人は先を行く目明きを何人追い越したかと嬉しそうに自慢したり、前から来る子どもたちの数を言い当てたりする。福市が「8人」だと言えば、徳市は「8人半だね」。これは赤ん坊を背負った子どもがいたため、徳市が正解。2人は目は見えなくても、足音や匂いや気配でたいていのことを察してしまうらしい。
「勘というやつを働かせないといけないよ、勘というやつを」
徳市の言葉である。
今度は、馬車が後ろから来て、彼らを追い抜いて行く。乗客は物静かな中年(佐分利信)と甥の少年、美しい女性(高峰三枝子)の3人だ。このときも勘の鋭い徳市はいい女だと指摘するだけにとどまらない。
「東京の女だね。東京の匂いがした」
ここまで、わずか5分ほど。しかも按摩2人が歩くだけのモノクロ映像である。にもかかわらず、画面からは新緑が匂ってくる。ゆるやかな移動撮影が、人と人がすれ違う刹那の心の揺れをとらえ、見えない徳一の目と東京から来た女の目が鮮やかに交差するようにも見えるのだ。

まもなく按摩2人は馬車の一行とひなびた温泉町で一緒になり、徳市は東京から来た女性の肩を揉む幸運にも恵まれる。この女性、美しいけれど、どこかワケあり風。演じる高峰三枝子は当時、19歳である。神秘的で、聖女のように近寄りが風情を漂わせながら、少し淫らな匂いもする。徳市が淡い恋心を抱くのも無理はないと思えるほど、『按摩と私』の高峰三枝子の雰囲気は艶っぽい。
やがて、温泉場の旅館で宿泊客のお金が盗まれる事件が相次いで起きる。勘のいい徳市は彼女を犯人と思い込み、大胆な行動に出るのだが……。
清水宏の映画の魅力の一つは自然光を生かした風景描写にある。たとえば、河原で遊ぶ少年と徳市や女性のやりとり。なんということのない描写なのに画面を気持ちのよい風が吹き抜けていく。風通しのいい余白が広がっているのだ。その余白に出会いや別れの切なさが小川のせせらぎのようにサラリと描かれ、絶品である。小津の映画を計算し尽くされた短編小説とすれば、清水宏の映画は即興を旨とする俳句の味わいに近い。
「小津先生の作品は、いろんな人があれこれ言いますが、清水オヤジのシャシンをきちんと評価する人がいないのは不思議でなりません」
これも『大船日記』にある笠智衆の言葉だが、2008年に『按摩と女』のリメイクが作られるなど清水宏の評価は年々高まっている。
文 米谷紳之介
「按摩と女」DVD絶賛発売中!ご自宅でもお楽しみください!


 ▼特設サイト「松竹映画100年の100選」
▼特設サイト「松竹映画100年の100選」  ▼「松竹・映画作品データベース」
▼「松竹・映画作品データベース」