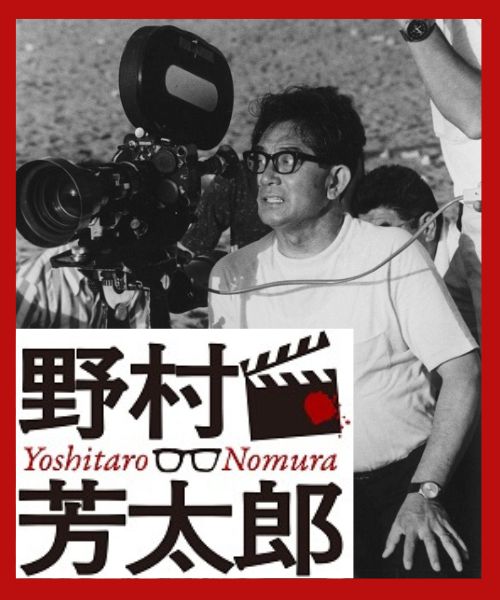連載コラム「銀幕を舞うコトバたち(11)」紀子さん、パン食べない? アンパン。
カテゴリ:コラム "銀幕を舞うコトバたち"

原節子が「紀子」の名前でヒロインを演じた、いわゆる「紀子三部作」のなかで、いや小津安二郎の全作品のなかで最も不思議な味わいがあるのが『麦秋』である。
紀子は『晩春』と同様に婚期を逸しかけている28歳の独身という設定で、彼女の突然の結婚を機に三世代同居の家族が離れ離れになっていく話だ。小津自身は「輪廻」や「無常」という主題を、余白を残しながら描いたと語っている。
余白から読み取れるものがあるとすれば、それは戦争や死だ。映画の公開は1951年だから、終戦からまだ6年。東山千栄子が演じる母は戦死した次男(紀子の兄)の復員を今も待っている様子だし、紀子は見えない力に動かされたかのように死んだ兄の同級生との結婚を決心する。まるで不在の兄があの世からこの世を見守っているような気配さえ漂い、全編に死という主題が静かに横たわっている。死は生の先にあるものではなく、いつも影のように生のそばにあるのだと言っているようだ。ラストの、麦の穂が揺れる畑の向こうを行く花嫁行列など、あの世ともこの世ともつかない淡い世界のようで、他の小津作品にはない奇妙な余韻が残る。
もう一つ、『麦秋』ならではの不思議な魅力に一役買っているのが食べ物だ。もともと小津の映画には食べたり、飲んだりするシーンが多いのだけれど、この作品は際立って多い。小さな孫が「おじいちゃん、ごはん」と祖父を呼びにくる朝食シーンで幕を開けると、劇中に次々と食べ物、飲み物が出てくる。
ビスケット、天ぷら、ビール、キャラメル、日本酒、ショートケーキ、サンドイッチ、ジュース、食パン、お茶漬け、すき焼き。さらに実際には出てこないが、登場人物の口をつくのが、コーヒー、鯛の浜焼き、焼き飯、寿司、アンパン、コロッケ。これらのなかで、観た人の記憶に確実に残るのがショートケーキとアンパンだろう。
ショートケーキは原節子が銀座で買ってきたもので、問題は900円という値段。当時の公務員初任給が6500円だから、べらぼうに高い。値段を聞いて、兄嫁役の三宅邦子が「食べるのいやになっちゃった」と愚痴をこぼす気持ちもよく分かる。
そして、このショートケーキの存在により、物語の終盤、杉村春子の口から出るアンパンの台詞が重要な意味を持ってくる。
小津ファンならよく知る名場面だ。杉村が息子(二本柳寛)を思い、夢みたないな話だけどと断りながら「あんたのような方がお嫁さんにきてくれたら、どんなにいいだろうって…」と切り出し、原はこの話を「あたしみたいな売れ残りでいい?」と直感的に承諾する。息子は翌日には秋田へ転勤する上、子持ちの身だ。杉村が喜びのあまり口走るのが「紀子さん、アンパン食べない? アンパン」という素っ頓狂な言葉である。
原にとって二本柳は小さい頃から身近すぎて、結婚の対象としてほとんど意識しなかった男と言っていい。その隠喩がアンパンだ。一方、ショートケーキが意味するのは、たとえば原の上司が持ちかけた縁談相手の名家の男。あるいは原の母が望む「田園調布の芝生のあるハイカラな家の奥さん」を実現してくれそうな男性。しかし、原は後者を人生の伴侶には選ばなかった。
少し乱暴な言い方をしてしまうと、『麦秋』は原節子がショートケーキ(優雅な生活を保障してくれる金持ちの男性)ではなく、アンパン(近くにいる、よく知った男性)を選ぶ物語である。小津はありふれた日常のなかのごく身近な場所にこそ自分にとって一番大切な人はいるし、一番大切なものはあると言いたかったのだと思う。
文 米谷紳之介
『麥秋』 ブルーレイ 5,170円(税込)
ブルーレイ 5,170円(税込)
発売・販売元:松竹
©1951/2016 松竹株式会社
松竹ストア内 松竹DVD倶楽部はこちら