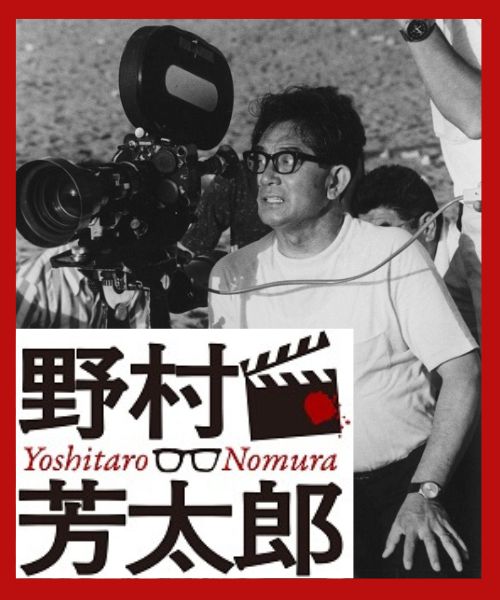「晩春」デジタル修復レポート第二回【笠智衆が猫の目に…】
カテゴリ:デジタル修復

「晩春」の監修を任された撮影監督の近森眞史は原盤の状態について、こう語る。
「お手上げですよ。画面では雨がザーザー、画面が揺れる。つまり、傷が多い。埃が付いている。すごく状態が悪いわけです。フィルムは暑さ、寒さで伸縮してしまい、形が変わってしまう。そうすると、フィルムの穴に入っていかないわけで、どんどんずれていき、揺れが起こる。
今ではフィルムセンターの保管庫から外に出すのに、3日かかるような厳重な管理をしていますが、昔の映画会社は管理が悪かった。一回封切ったら終わりというのが常識でしたからね。こんな時代が来るとも思っていなかったわけです」
松竹映像センターの五十嵐真も「オープニングの音楽が飛んでしまっていました。音に関しては、別のフィルムを使っています」と証言する。
フィルムは適切な温度と湿度で保管して初めて、公開当時の鮮やかな色やコントラストと音響を鑑賞できる。長い期間を経過した作品は、当時の保管・利用状況が主な原因で、傷み、色あせてしまう。
公開当時に「晩春」を見たというある松竹幹部も「当時は一番館で上映されて、二番館、三番館といった具合にフィルムが回っていくわけです。当時は三八番館まであったと記憶しています」と振り返る。つまり、人気作であればあるほど、フィルムは使い回しされ、劣化は激しかった。
特に状態のひどいものでは、笠智衆の顔が引き伸ばされて、目は漫画の猫の目のようになっていたり、着物の柄もよく見えなかった。「原盤となったのはオリジナルをコピーしたもの。コピーを続けていくと、画の柔らかさが消えて、グラデーションがくっきりとした階調になってしまうんです。修復前のフィルムをお見せしたいですよ。そうすれば、修整がどんなに大変だったのか分かってもらえますから」(近森)
近森と五十嵐がこだわったのは、モノクロの階調だった。本作は名カメラマン厚田雄春(1905〜1992)によるものだ。「厚田さんの画はよく硬いと言われていたけども、そこまで硬くはない。『麦秋』(1951)の画が印象に残っていて、そこを手本にしました」(近森)。「東京物語の予告編は奇跡的にオリジナルが残っていたんです。これはブルーレイにも収録しているんですが、見ると、明らかに柔らかい画調なんです。そこを目指そうということになりました」(五十嵐)。
その修復を手掛けるのは、米ニューヨークのシネリック社に決まった。近森と五十嵐は2014年12月、期待と不安を抱きながら、ニューヨークへと渡り、そのバトンをアメリカ人に託した。(敬称略)
「晩春」デジタル修復版は、「東京物語」、「秋刀魚の味」のデジタル修復版とともに『松竹120周年祭』で11月21日(土)~27(金)に東京の東劇にて上映。