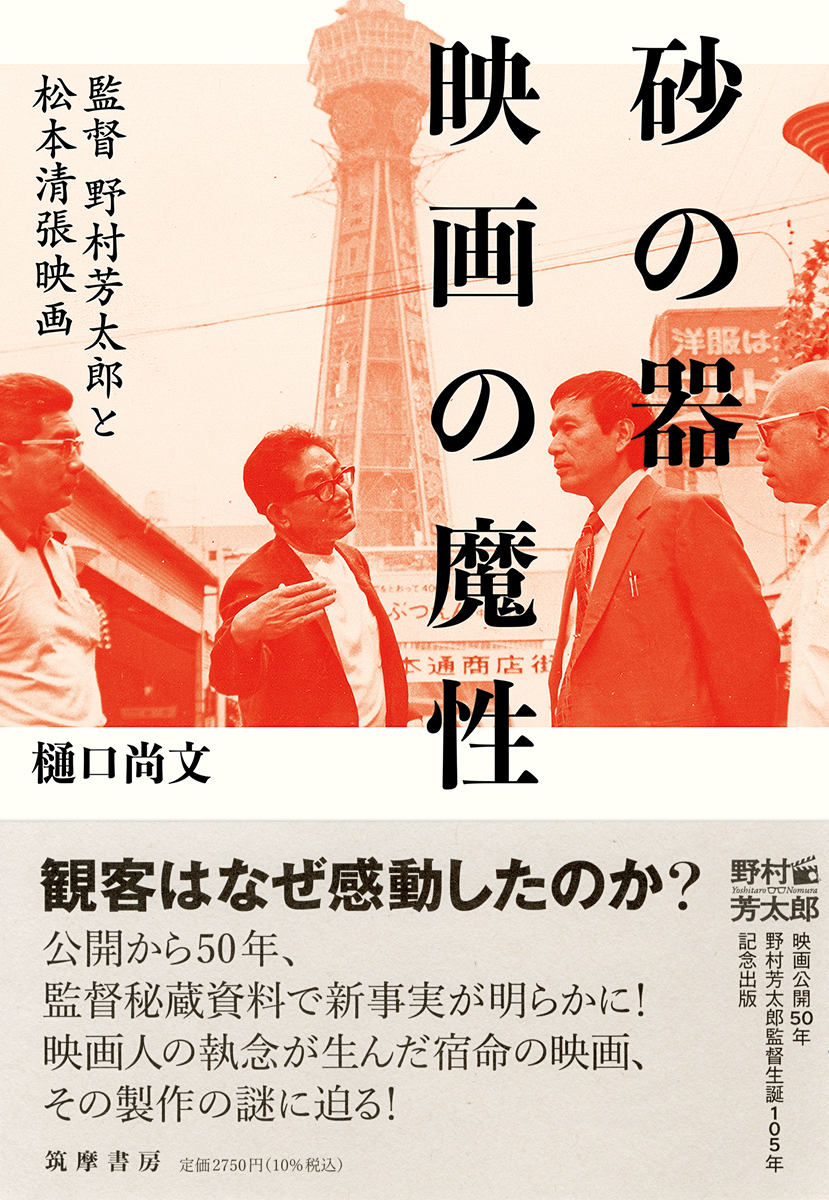連載コラム「銀幕を舞うコトバたち(56)」
俺みたいないいかげんな男と出会って損したわけだね。
カテゴリ:コラム "銀幕を舞うコトバたち", 松竹映画100周年
昭和の映画スターのプロフィールを見ていて何より驚かされるのは出演作品の数だ。たとえば、高倉健である。1976年に東映を退社し、フリーとなってからはペースとしては1年に1本も出てないのに、生涯の出演作は200作に近い。1950年代から1960年代の日本映画が隆盛だった時代に、いかに多くの作品に出ていたかが分かる。
高倉健より2つ年下だが、デビューは5年早かった岡田茉莉子も当然ながら出演作は多い。谷崎潤一郎を名付け親に1951年にデビューすると、順調にキャリアを重ね、1962年には100作に達した。すごいのはその100作目を29歳の若さで自らプロデュースしていることだ。原作は早い時期から藤原審爾の『秋津温泉』と決め、監督には当時、若手監督だった吉田喜重を起用。その眼力が確かだったことはその後、岡田・吉田のコンビで『エロス+虐殺』や『告白的女優論』など数多く秀作が生まれたことが証明している。

『秋津温泉』は太平洋戦争末期、空襲によって焼け落ちた岡山の描写から始まる。結核を患い、人生に絶望した河本周作(長門裕之)は、列車で知り合った女の案内で山あいにある秋津温泉の旅館「秋津荘」にたどり着く。
周作の病状は医者にも見放されるほどひどく、それを秋津荘の一人娘、新子(岡田茉莉子)が甲斐甲斐しく看病する。彼女の溌剌とした個性が、生きる意欲を失った周作の気持ちを少しずつ変えていく。
1945年8月15日。戦争に負けたことを知った新子は大声で泣く。その涙が周作に生きる力を取り戻させることになる。
「ぼくは秋津温泉がぼくの死に場所だと思って……なんだかそんな気がして上ってきた。でも、今、ぼくは死なない。あなたに生きることを教わった」
その後、周作は4度、秋津を訪れるのだが、彼を慕う新子の気持ちに反するように、どんどん俗化し、つまらない中年男に成り下がっていく。彼の言葉にもそれは顕著だ。
3年後に現れた周作は文学に身を投じており、すっかり厭世家きどりである。
「ぼくは何もかも煩わしいんだ。あなたも煩わしい。ぼく自身が生きていることが煩わしいんだ」
2人は心中を試みるが失敗に終わり、周作は新子の母の差し金で岡山に帰されてしまう。
それから3年後。周作は結婚した。生活は楽ではなく、仲間が文学賞を受賞したことを妬んでいる。秋津荘の女将となった新子と会っても愚痴しか出てこない。
「生活も荒れ、気持ちも荒れてる。あなたに言われるまでもなく、俺は変わったよ」
さらに4年後。東京の出版社への就職が決まった周作は赴任する前に、やはり秋津にやってくる。
「今だって生きてるのか、死んでんだか……大差ないけどね」
「俺みたいないいかげんな男と出会って損したわけだね」
なんとも無責任な周作に、それでも新子は必死にすがるが、周作は立ち去る。
最後の逢瀬は1962年。初めて会った日から17年の時間が流れていた。34歳になった新子は秋津荘を手離すことも決まり、人生に疲れ果てている。それまでは新子が周作の来訪を知って着物姿で走るシーンが繰り返し描かれたが、そんな明朗快活な新子はもういない。笑顔も消えた。

今度は新子から心中を持ちかける。
「死んで。私と死んで」
周作の言葉は冷ややかだ。
「生きるとか死ぬとかってぇのはね、そんなのは昔のことなんだ」
都会の文学青年だった周作は山奥の温泉で生きるしかない新子にとってずっと心の拠り所だった。しかし周作は自分の都合でしかやって来ないうえ、会うたびに自堕落になっている。「待ち続ける女」と「気まぐれに姿を現す男」。互いに依存しながら、最後までその距離が埋まることはない。

男と女を絵画のような構図に配した映像にかぶせられるのは、林光の哀しみを帯びた劇的な旋律である。その旋律が反復されることにより画面はどんどん不穏な気配に包まれる。愛とは人を蝕み、ときに人を死に追いやるもの。岡田茉莉子の大きな瞳が一途な女の心の変化を見事に表現している。
文 米谷紳之介
『秋津温泉』DVD絶賛発売中!ご自宅でもお楽しみください!