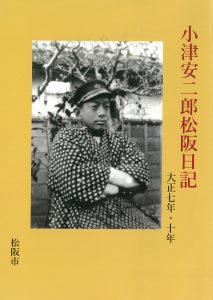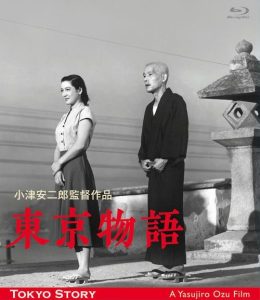連載コラム「OZU活のすすめ」第10回 ~松阪編 小津安二郎が暮らした愛宕町 思い出の神楽座跡を歩く~
カテゴリ:連載コラム「OZU活のすすめ」
皆さまこんにちは。今回から松阪編として、小津監督が少年時代を過ごした三重県松阪市の小津スポットをご紹介します。

伊勢市を後にし、松阪市にやって来ました。小津監督にとって思い出深い「松阪の停車場」です。中学時代は寄宿舎で生活した小津監督ですが、中学5年生の1学期に停学処分となり、そのまま寄宿舎を退舎させられてしまいます。2学期から卒業までは、松阪の自宅から毎日汽車で通学しました。

松阪駅から徒歩15分程、小津監督の家があった愛宕町の街並みです。大正2年3月、小学3年生を修了した小津監督は、家族と共に父の生まれ故郷である松阪に移住しました。移住に際し、小津監督の父・寅之助さんは飯南郡松阪町垣鼻(現松阪市愛宕町) に土地と家を購入しました。伊勢街道に面した大きな家で、家の裏には広い庭と蔵がありました。小津家はこの家で約10年間暮らすことになります。
小津監督が暮らした愛宕町はどんな町だったのでしょうか。小津監督の兄・新一さんのインタビューや大正時代の松阪について書かれた資料を元に、当時の様子を見てみましょう。
愛宕町の朝は賑やかな物売りの声で始まります。毎朝、近郷の農家が野菜などを積み込んで松阪へ売りにやって来ました。松阪の東端にある愛宕町は伊勢方面からの玄関口。愛宕町に到着すると皆が大きな声で品々を売り歩きます。
「だいこっきゃーどうかなー」
「噛んでも噛んでも噛み切れないこんにゃくはどうかなー」
小津家の子供達も、まだ夜が明けきらぬ頃からこの賑やかな声で目が覚めたそうです。
大正時代の市街地図を見ると、愛宕町には雑貨店、足袋店、金物店など数多くの商店が軒を連ねています。松阪に住む人だけでなく、商売等で松阪に出てくる人を顧客とする商店も相当数あったといいます。午後になると、松阪を発つ前に生活用品や土産などを買い求める人々で大いに賑わったのではないでしょうか。
夕暮れになると通りには三味線の音が響き始めます。伊勢街道の宿場町だった松阪は、古くから街道を行き交う多くの旅人で賑わいました。松阪の東西の玄関口には遊郭が発展し、西側の川井町は西廓、東側の愛宕町は東廓と呼ばれていました。愛宕町は民家や商家の間に料亭や妓楼が並ぶ、華やかな一帯でもありました。

大正2年4月、小津監督は松阪町立第二尋常小学校(現松阪市立第二小学校)4年生に転入しました。現在小学校は1km程離れた場所に移転していますが、小津監督が通った校舎跡は五十鈴公園として整備されています。
転校当初、小津監督は松阪の少年達と中々打ちとけなかったといいます。小津監督が生まれた小津新七家は、松阪の豪商・小津与右衛門家の分家であり、肥料問屋「湯浅屋」の支配人を代々務める家系でした。小津監督は東京から来た名家の子供として、ちょっぴり敬遠されていたようです。小津監督も、新しい環境や松阪の方言に慣れるまでには時間が必要だったのかもしれません。
とはいえ、隣家に住む2歳下の男の子を始め、小津監督にも多くの友達ができました。家の庭には寅之助さんが作った砂場や鉄棒があり、近所の子供達が遊びに来るようになります。また、裏木戸の傍には築地塀に囲まれた一角があり、子供達に「おんばのふところ」と呼ばれていました。ここは風の当たらない暖かな陽だまりとなり、子供達は冬になると凧上げや独楽回しを楽しみました。

旧小津家の裏手にある菅相寺(かんしょうじ)は、地元の方々から愛宕の天神さんと呼ばれ親しまれています。明治時代中期に建てられた本堂は、小津監督が暮らした頃と変わらぬ佇まいです。裏木戸を飛び出してすぐ駆けていける天神さんの境内は、小津監督にとって格好の遊び場だったのではないでしょうか。伊勢街道から菅相寺へ続く小路は天神小路と呼ばれ、小津監督が小学6年生の時に書いた作文にその名を見ることができます。

菅相寺の隣には200年の歴史を持つ料亭「武蔵野」があります。文政3年に広月楼の名で創業した武蔵野は、十数人の抱え芸妓を擁し、松阪の名士や文化人が集う格式高い料亭でした。
昭和に入ると店名を武蔵野と改め、料理旅館となります。八代目当主の竹中さんに、「武蔵野」の名の由来をお聞きしました。ある時、広月楼を訪れた歌人がお座敷で歌を詠んだそうです。その時詠まれた「武蔵野」の歌が由来になったとのこと。大正7年の小津監督の日記に「むさし」と書かれていることから、大正時代には既に武蔵野という呼称が定着していたのかもしれないと仰っていました。昭和34年、『浮草』のロケハンで志摩半島を訪れた小津監督が、同行したスタッフと共に武蔵野に宿泊しています。

料亭に併設されたレストランでは季節のお弁当や揚げたての天ぷらなど、旬の食材を活かしたお料理を気軽に楽しむことができます。散策の途中にレストランで豆腐料理のコースをいただきました。

私は冷奴、田楽、湯豆腐の中から、田楽をお願いしました。濃厚な甘味噌に山椒がピリッと効いています。これからの季節は熱々の湯豆腐もいいですね!秋らしい柿やきのこの白和えは、上品な和え衣が柿の甘みを引き立て、とても美味しかったです。

天神小路を辿り再び伊勢街道へ。愛宕町集会所のシャッターには小津監督の大きな笑顔がペイントされていました。さすが小津監督ゆかりの町です。集会所の隣にある木造の建物は、鰻が名物の「井筒」という料理店でした。井筒の歴史は古く、文化8年に書かれた文献に既にその名が見え、江戸期には松阪や伊勢の豪商達が頻繁に訪れる料亭でした。小津家に保管されていた書類には、井筒に料理を注文した領収書が複数あり、中には小津監督の誕生日に鰻を注文したものも残されています。

集会所がある交差点を右折すると、愛宕山龍泉寺の三門が見えます。龍泉寺は奈良時代に聖武天皇の勅命により建立され、戦国武将蒲生氏郷が松坂城を築城した際、現在の地に移建されました。古くから「あたごさん」の名で親しまれ、火防や良縁にご利益があるお寺として信仰を集めています。龍泉寺の門前には、小津監督が足繁く通った映画館「神楽座」がありました。
神楽座の前身は、歌舞伎の公演等を行う芝居小屋でした。明治30年3月、龍泉寺の近くにあった愛宕座が門前に移転し、小屋の名を神楽座と改めました。大正2年頃から映画の上映を始め、以降は映画興行が中心となっていきます。大正10年に内部を改装し、本格的な映画館となりました。

※絵葉書「伊勢松阪愛宕山龍泉寺山門(蒲生氏郷公設立)及神楽座」:個人蔵
写真は昭和初期に撮影された龍泉寺の三門と神楽座です。昭和5年公開の梅村蓉子主演『唐人お吉』と、嵐寛寿郎主演『鞍馬天狗』の幟が見えます。映画の幟が立っていますが、絵看板が掲げられた神楽座は芝居小屋の雰囲気を色濃く残しています。恐らく小津監督が通った大正10年頃と変わらぬ佇まいではないでしょうか。
小津監督は中学4年生頃から映画館に通い始め、汽車通学をするようになってからは、教師の目が届かない松阪の映画館に通い詰めました。中学卒業を前にした5年生3学期の日記を見ると、さすがに試験期間中は控えていますが、週末だけでなく平日の夜も映画館に出かけている様子が窺えます。教師に見つかる心配がなかったとはいえ、流石に学生服で映画館に入ることは憚られたのか、井筒の2階で学生服から私服に着替えて映画を見に行ったという話が伝わっています。
小津監督が夢中になったのは、当時流行した「連続活劇」と呼ばれる形式の映画でした。全15~20篇のストーリーから成り、毎週2篇ずつ新しいエピソードが封切られるという、連続ドラマのようなシステムでした。内容はハラハラドキドキの活劇(アクション)やスリリングな探偵劇。毎回エピソードの終盤に主人公が絶体絶命のピンチに陥り、続きは来週のお楽しみ!となるのがお決まりでした。これは続きが気になって映画館に通ってしまいますね。
大正10年の小津監督の日記には、神楽座で上映された連続活劇のタイトルが並んでいます。3月から5月にかけては、小津監督が大ファンだったパール・ホワイト主演『呪いの家』(※原題『The House of Hate』)が上映されました。パール・ホワイトは「連続活劇の女王」といわれ、スタントなしでアクションシーンを演じる人気スターでした。麗しい美貌と抜群の運動神経でアクションをこなす快活さ。パールが演じる新しいヒロイン像は評判となり、多くの連続活劇に出演しました。
大正10年5月12日(木)
一略一
夜は乾と呪いの家の最終篇を見に行つた。
又懐かしいパールと暫く別れねばならない。
『呪いの家』最終篇を鑑賞した日の日記には、パールとの別れを惜しむ記述があります。私達も毎週楽しみにしているテレビドラマが終了すると、何とも言えない喪失感を覚えますね。小津監督の切ない気持ちがとてもよく分かります。
昭和26年11月14日、47歳の小津監督は脚本家の野田高梧さんと松阪を訪れ、愛宕町の旧宅に宿泊しました。その夜、小津監督は野田さんを神楽座に案内し、こんな話をしたといいます。『もしこの小屋がなかったら、僕は映画監督になってなかったと思うんですよ』
小津監督にとって神楽座は、映画の面白さを知り、後の人生を決定付けた特別な場所だったのでしょう。
昭和26年12月16日、小津監督の母校である第二小学校が火元となり、後に松阪大火と呼ばれる大規模な火災が発生しました。強風に煽られた火の粉は風下の愛宕町に降り注ぎ、町は瞬く間に炎に包まれました。懐かしい神楽座、井筒、武蔵野、そして小津家の旧宅も蔵だけを残して焼失しました。小津監督が野田さんを神楽座に案内してから僅か1ヶ月後の出来事でした。

龍泉寺の三門は安土桃山時代の様式を示す貴重な建築物として、県指定有形文化財となっています。側面の破風には、昭和26年の松阪大火で黒く焼け焦げた跡が残り、炎の激しさを伝えています。先々代の御住職が門の上から懸命に水をかけ、燃え盛る門前から命懸けで寺への類焼を食い止めたそうです。現在は区画整理によって龍泉寺の隣に国道が通り、景観が大きく変わっています。神楽座があった当時の面影はありませんが、松阪にお越しの際はぜひ龍泉寺を訪れ、小津監督の夢と青春が詰まった神楽座に思いを馳せてみてください。
ところで、松阪は「まつざか」ではなく「まつさか」と読み、地元の方言では「まっつぁか」や「まっさか」と呼ばれます。昭和28年に公開された『東京物語』の中に印象的なシーンがあります。
.jpg)
母が危篤となり、子供達が広島県尾道市の実家に駆けつけます。しかし、大阪で働く三男の敬三が中々現れません。翌朝、母が息を引き取った後にやっと到着した敬三のセリフです。
「生憎くと松阪の方に出張しとりましてな。おくれましてどうもすんません」
小津監督は、敬三に敢えて「まっつぁか」と言わせています。リアルな方言がセリフに生命を吹き込んでいます。しかし尾道出身の敬三が松阪の方言を喋るのは何だか不思議な気がします。小津監督は懐かしい松阪への想いを敬三に投影させたのでしょうか。
次回からも小津監督が駆け回った「まっつぁか」の小津スポットや、小津家ゆかりのお店などを紹介していきます。OZU活松阪編もよろしくお願いいたします!
日記文引用:「小津安二郎松阪日記」
物売りの声引用:「陽のあたる家」井上和夫編 フィルムアート社刊
文:ごとう ゆうこ
「小津安二郎松阪日記」について詳しくはこちら https://www.city.matsusaka.mie.jp/site/culture-info/ozuyasujirou.html
『東京物語』作品ページはこちら https://www.cinemaclassics.jp/ozu/movie/2851/
小津安二郎監督公式サイトはこちら https://www.cinemaclassics.jp/ozu/